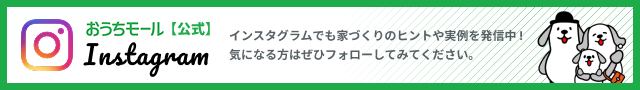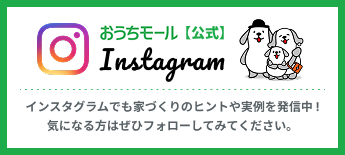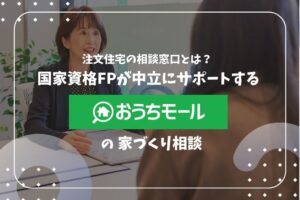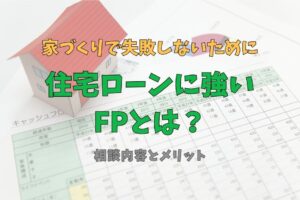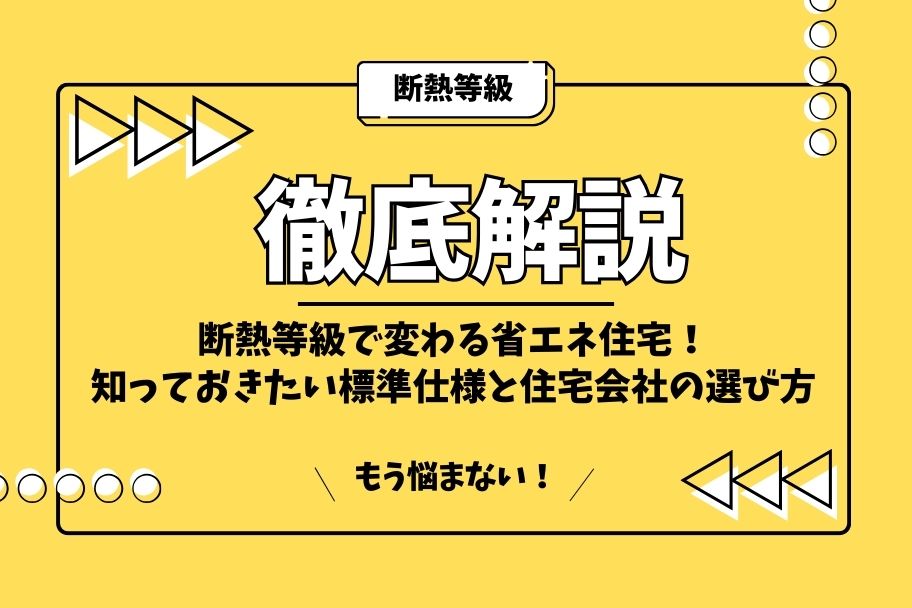
この記事を読むのに必要な時間は約 20 分です。
【徹底解説】断熱等級で変わる省エネ住宅!知っておきたい標準仕様と住宅会社の選び方
■ 高断熱住宅が求められる理由とメリットをお伝えします。
■ 断熱等級の高い家を建てる際の住宅会社の選び方をご紹介します。
「断熱等級」(正式名称:断熱等性能等級)は、これからの住宅選びで最も重要な指標の一つです。本記事では、省エネ住宅の基礎となる「断熱等級」の役割から、等級4から等級5、さらに等級6・7まで、それぞれの基準と評価指標「Ua値」を徹底解説。高断熱住宅がもたらす光熱費削減や快適性といった具体的なメリットもご紹介します。あなたの理想の省エネ住宅を実現するための「標準仕様」の理解、そして失敗しない「住宅会社の選び方」まで、この解説を読めば、後悔しない家づくりのヒントが見つかるでしょう。
\ 国家資格を持つアドバイザーが家づくりをサポート!/
1. 注文住宅の「断熱等級」とは?省エネ住宅の基礎知識
家づくりをする上で、住まいの快適さにこだわりたいなら断熱性能にこだわることをおすすめします。
断熱性能を高めたマイホームなら、夏涼しく冬暖かい空間で快適な暮らしを送ることができます。
断熱性能のランクを具体的に表したものが「断熱等級」(正式名称:断熱等性能等級)です。どの等級の家を建てるかによって、建物の快適性やかかる光熱費は大きく変わります。
そこで、まずは断熱等級の基礎知識について解説します。
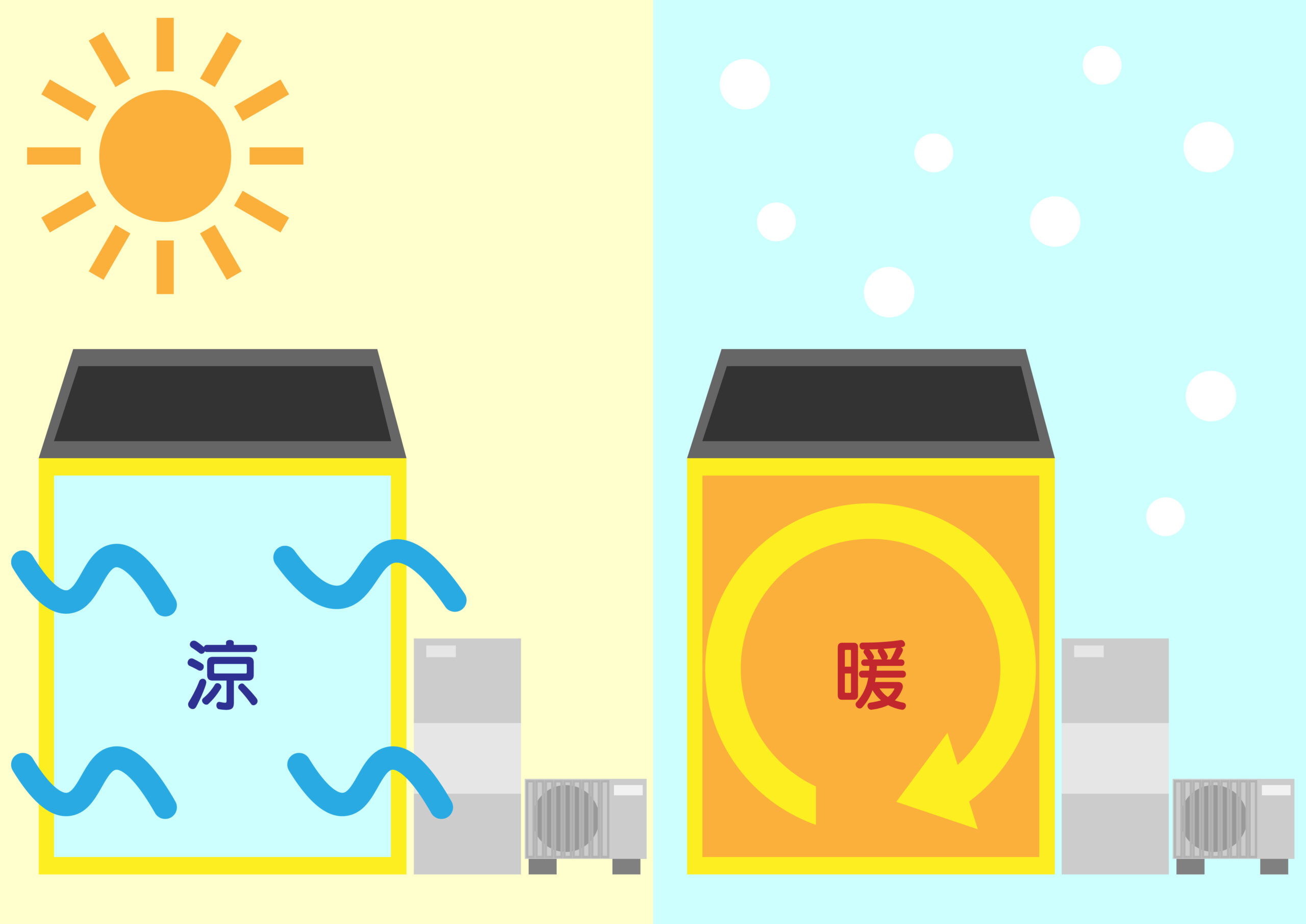
1.1 住宅性能表示制度における断熱等級の役割
断熱等級は、住宅の性能を等級で分かりやすく表示する「住宅性能表示制度」の項目の1つです。
この制度は、設計された建物に対して、第三者である「登録住宅性能評価機関」によって客観的に評価を行い、その結果を「住宅性能評価書」として交付することで、住宅の性能を消費者が比較検討しやすくすることを目的としています。
断熱等級は、外壁や窓などからの熱損失をなるべく少なくするために、対策をどの程度行っているかを等級で評価したものです。外壁や窓の断熱性能が高いほど、熱が逃げにくい建物として、高い等級が認定されます。
これにより、購入者は住宅の省エネ性能を数値で把握でき、快適性や光熱費削減効果を事前に予測できます。
参考ページ:新築住宅の住宅性能表示制度ガイド|国土交通省
1.2 断熱等級の歴史と最新動向:等級4から7まで
現在、断熱等級は1〜7まであり、かつて最高だった等級4から段階的に進化してきました。
1.2.1 1999年制定「断熱等級4」の基準と特徴
次世代省エネ基準を満たす性能で、複層ガラスの採用が必須。
等級1に比べ約60%の省エネを実現し、年間8万円前後の冷暖房費削減につながるとされます。
1.2.2 23年ぶりの新基準「断熱等級5」の登場
2022年4月、等級4以来23年ぶりに「断熱等級5」が追加されました。これにより、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準の性能を満たす建物が新たに評価対象となりました。
等級5は、等級4に比べてさらに熱損失を抑えることが条件です。具体例として、6地域の場合:
- 等級4:アルミ樹脂複合サッシ+透明複層ガラス
- 等級5:アルミ樹脂複合サッシ+Low-E複層ガラス
等級5を取得するには、ガラスにLow-E膜を採用する必要があります。
また、断熱材の厚みも強化されます。例として:
| 等級4 | 等級5 | |
|---|---|---|
| 天井 | 高性能グラスウール16K(155mm) | 吹込み用グラスウール18K(210mm) |
| 壁 | 高性能グラスウール16K(85mm) | 高性能グラスウール16K(105mm) |
| 床 | 高性能グラスウール24K(105mm) | ・内側:高性能グラスウール24K(42mm) ・外側:高性能グラスウール24K(80mm) |
このように使用する断熱材や厚みが大きく異なります。ただし、内容は住宅会社によって違うため、採用している断熱仕様と取得等級を必ず確認しましょう。
参考ページ:③住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度におけるZEH水準を上回る等級について|国土交通省
1.2.3 さらなる高みへ「断熱等級6・7」の基準
2022年10月には、さらに高性能な 等級6・7 が新設されました。
- 等級6:省エネ基準比でエネルギー消費量▲30%
- 等級7:省エネ基準比でエネルギー消費量▲40%
実現には、より厚い断熱材や高性能サッシが必要です。電気代高騰や環境配慮の観点から、今後はこれらの高等級が求められていくでしょう。
2. 断熱等級の評価基準「Ua値」とは?
住宅の断熱性能を数値で示す指標が「Ua値(外皮平均熱貫流率)」です。
数値が低いほど熱の出入りが少なく、断熱性能が高いことを意味します。
2.1 Ua値の計算式
Ua値=「屋根・天井・壁・床・窓」からの熱損失量の合計 / 外皮合計面積
快適な室内環境や省エネ住宅を実現するには、このUa値を低く抑えることが重要です。
2.2 地域区分ごとのUa値基準と求められる断熱性能
日本は8つの地域区分に分かれ、寒冷地ほど厳しいUa値が求められ、温暖地では基準が緩やかになります。
例:断熱性能基準(Ua値)
| 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | |
|---|---|---|---|---|
| 地域1(北海道など寒冷地) | 0.46 | 0.40 | 0.28 | 0.20 |
| 地域4(愛知県豊田市稲武町・設楽町津具など) | 0.75 | 0.60 | 0.34 | 0.23 |
| 地域5(愛知県設楽町・東栄町など) | 0.87 | 0.60 | 0.46 | 0.26 |
| 地域6(愛知県中心部など) | 0.87 | 0.60 | 0.46 | 0.26 |
| 地域7(豊橋市など) | 0.87 | 0.60 | 0.46 | 0.26 |
お住まいの地域に合った断熱性能を採用することが大切です。詳しい区分は国土交通省の資料を確認してください。
参考ページ:地域区分新旧表|国土交通省
2.2.1 あなたの地域の必要Ua値は?地域区分を確認しよう
建築予定地がどの地域区分に該当するかを確認し、必要なUa値を把握することは、適切な住宅会社選びの第一歩です。
愛知県は、一部の市町村を除き、多くの地域が区分6に分類されています。
| 地域区分 | 該当市町村(愛知県) |
|---|---|
| 4地域 | 豊田市(旧稲武町に限る)、設楽町(旧津具村に限る)、豊根村 |
| 5地域 | 設楽町(旧設楽町に限る)、東栄町 |
| 6地域 | 名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市(旧稲武町を除く。)、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町 |
| 7地域 | 豊橋市 |
愛知県で断熱等級5を確保するには、全地域で Ua値0.60以下 が必要です。どの等級を目指すかによって、建物の予算や会社選びも変わります。
2.2.2 地域別!断熱等級5達成のための標準仕様例
断熱等級5は、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準に相当する高い断熱性能を示します。愛知県の地域4〜7では、Ua値0.60を確保することで断熱等級5を取得可能です。ここでは、このUa値0.60を達成するために必要となる断熱材の厚さやサッシの断熱性能について、標準的な仕様例をご紹介します。
- サッシ:アルミ樹脂複合サッシ+Low-E複層ガラス
- 断熱材(地域6の場合の一例)
| 部位 | 断熱等級5(標準仕様例) |
|---|---|
| 天井の断熱材 | 吹込み用グラスウール18K(210mm) |
| 壁の断熱材 | 高性能グラスウール16K(105mm) |
| 床の断熱材 | ・内側:高性能グラスウール24K(42mm) ・外側:高性能グラスウール |
3. なぜ今、高断熱な省エネ住宅が求められるのか?
地球温暖化対策や電気代の高騰を背景に、住宅には高断熱・省エネ性能が強く求められています。もはや選択ではなく「必須」といえる状況です。
3.1 2025年義務化!断熱等級4以上の必要性
政府は、2025年4月以降の新築住宅に断熱等級4以上を義務化する方針を打ち出したのです。
これは1999年の「次世代省エネ基準」に相当し、最低限の断熱性能を確保する水準です。
新築を検討する際は、必ず断熱等級4以上に対応しているかを確認しましょう。
3.2 高断熱住宅がもたらす5つのメリット(快適性・健康・光熱費削減など)
高断熱住宅は義務化に対応するだけでなく、実際に住む人に快適さや経済性など大きなメリットをもたらします。
3.2.1 快適な空間で生活できる
外気の影響を受けにくく、夏は涼しく、冬は暖かい。部屋ごとの温度差も少なく、一年中どこにいても快適です。
3.2.2 熱中症やヒートショックの危険性が減る
温度差が小さいため、冬のヒートショックや夏の熱中症リスクを抑え、安全な住環境を実現します。
3.2.3 光熱費を抑えることができる
断熱性が高いほど冷暖房効率が良くなり、エネルギー消費を大幅にカット。年間数万円規模で光熱費を節約できます。
3.2.4 結露しにくく家が劣化しにくい
断熱性が低い家に多い結露を防止。カビやダニの発生を抑え、健康被害や建物の劣化を防ぎます。
3.2.5 補助金・優遇制度を活用できる
結露や腐食を防ぐことで建物が長持ちし、将来の修繕費も削減。省エネ性能の高さは資産価値の維持にもつながります。
代表的な制度には、以下のようなものがあります。(制度は時期によって変動する場合があります)
| 制度名 | 主な対象 | メリット |
|---|---|---|
| 住宅ローン控除 (住宅借入金等特別控除) |
省エネ基準適合住宅、ZEH水準省エネ住宅、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅など | 住宅ローンの年末残高に応じて所得税から控除される金額が優遇されます。特にZEH水準や長期優良住宅は、一般の住宅よりも借入限度額や控除率が優遇される場合があります。 |
| ZEH補助金 (ZEH支援事業) |
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の要件を満たす住宅 | 一定の要件を満たすZEH住宅に対して、定額の補助金が交付されます。 |
| 地域型住宅 グリーン化事業 |
長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH等、地域材を使用した住宅など | 地域の中小工務店が建てる高性能な木造住宅に対し、補助金が交付されます。 |
これらの制度を賢く活用することで、高断熱住宅の取得コストを抑え、より高性能な住まいを実現することが可能になります。住宅会社選びの際には、これらの補助金制度への対応状況についても確認すると良いでしょう。
\ 資金計画もメーカー比較・紹介もすべて完全無料です/
4. 断熱性能の高い住宅を建てる!住宅会社の選び方
断熱性能に力を入れている会社には共通点があります。これを知ることで、省エネ性能の高い住宅を建てられる会社を見極めやすくなります。
4.1 断熱性能に強みを持つハウスメーカーの特徴
4.1.1 高い技術力と研究開発への投資
独自の工法や高性能断熱材(ウレタンフォーム・フェノールフォーム等)を採用。自社研究施設や大学との連携で最新技術を追求している。
4.1.2 標準仕様で高い断熱性能等級に対応
多くは等級4ですが、強みを持つ会社は、「断熱等級5」や「断熱等級6」を標準仕様に。追加費用を抑えながら高性能住宅を実現できる。
4.1.3 設計と施工の一貫体制
断熱性能は施工精度が重要。設計・施工部門が連携し、自社で気密測定を行い数値を公開している会社は信頼性が高い。
4.1.4 豊富な実績と具体的な数値の提示
施工事例が豊富で、Ua値(外皮平均熱貫流率)やC値(隙間相当面積)といった具体的な性能数値を明確に示し、根拠を説明できる。
4.1.5 省エネ住宅に関する補助金制度への対応
ZEH補助金や地域型住宅グリーン化事業など、省エネ住宅の補助金に関する情報提供や申請サポートに積極的。
4.2 失敗しない!住宅会社選びで確認すべきポイント
断熱性能に強い家を建てるには、以下をチェックしましょう。
| 確認ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 断熱性能の数値と根拠 | 提案された住宅のUa値、C値を具体的に提示してもらいましょう。単に「高断熱」と謳うだけでなく、計算書やシミュレーション結果など、数値の根拠を明確に説明できるかが重要です。 |
| 標準仕様とオプション | どの断熱等級が標準仕様なのかを確認し、それ以上の性能を求める場合の追加費用も把握しましょう。断熱材の種類、厚み、窓のサッシやガラスの仕様(Low-E複層ガラス、トリプルガラスなど)も具体的に確認します。 |
| 気密測定の実施有無 | C値(隙間相当面積)は施工精度に大きく左右されます。引き渡し前に気密測定を実施しているか、またその結果を施主に開示するかを確認しましょう。C値の保証があるとなお安心です。 |
| 設計の自由度と提案力 | 省エネ性能だけでなく、間取りやデザインなど、施主の要望をどれだけ実現できるかも重要です。高性能とデザイン性を両立できる提案力があるかを見極めましょう。 |
| 費用と予算の明確化 | 高性能住宅は初期費用が高くなる傾向があります。見積もりの内訳が明確か、追加費用が発生しにくいかを確認しましょう。また、光熱費削減効果や補助金活用による実質的なコストメリットについても説明を求めましょう。 |
| 保証・アフターサービス | 住宅の性能に関する保証(例:断熱性能保証)があるか、また、引き渡し後の定期点検やメンテナンス体制が充実しているかも確認が必要です。長期的な安心感につながります。 |
| 担当者の知識と対応 | 断熱性能や省エネ住宅に関する専門知識が豊富で、質問に対して的確かつ分かりやすく説明してくれる担当者を選びましょう。信頼できる担当者との出会いは、家づくりの成功に不可欠です。 |
| 第三者機関による評価 | 住宅性能評価書やBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)評価など、第三者機関による客観的な評価を受けているかも確認ポイントです。これにより、住宅の性能が公的に認められていることが分かります。 |
| 複数社での比較検討 | 複数の住宅会社から相見積もりを取り、提案内容や費用、対応などを比較検討することが大切です。住宅展示場や完成見学会に足を運んだり、中立的な立場でアドバイスをしてくれる「注文住宅の相談窓口」を活用するのも良い方法です。 |
これらのポイントを総合的に判断し、ご自身の理想とする住宅を、安心して任せられる住宅会社を見つけましょう。
5. まとめ
断熱等級は、これからの住まいづくりにおいて欠かせない要素です。高断熱な住まいは、冬暖かく夏涼しい快適な暮らしを実現し、健康維持にも寄与するだけでなく、長期的な光熱費削減にも直結します。等級5以上の高性能住宅を選ぶことで、より高い快適性と経済性を享受できます。理想の省エネ住宅を実現するためには、Ua値や地域区分を理解し、何よりも断熱性能に強みを持つ信頼できる住宅会社を慎重に選ぶことが成功の鍵となります。
注文住宅の相談窓口「おうちモール」では、40社以上の住宅会社の「価格」や「特徴」を一気に比較・検討ができるため、希望に見合う住宅会社を事前に見定めることができます。まずはお気軽にご相談ください!
おうちモールは、FPや宅建などの国家資格を持つプロのアドバイザーが
あなたにピッタリの住宅会社をご紹介する注文住宅の相談窓口です。
\ 資金計画相談もメーカー比較・紹介もすべて完全無料です /
おうちモール公式サイトへ
住宅展示場で注文住宅の後悔はもうしない!失敗談から学ぶ賢い見学ガイド
前の記事へ
注文住宅の費用相場ガイド:1,000万~3,000万円台の予算と30坪・40坪の広さで建てるローコスト住宅の秘訣

次の記事へ