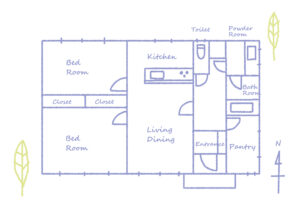この記事を読むのに必要な時間は約 19 分です。
ペアローンはやめた方が良い?!メリット・デメリット、収入合算との違いも解説!
マイホームを建てる際には、住宅ローンを利用する方が多いです。住宅ローンにもさまざまな種類があり、その1つに「ペアローン」があります。ペアローンは共働き世帯や親子などの2名でローンを組むという借入方法で、「住宅ローン控除を2名それぞれが利用できる」などメリットがあります。ただし、「どちらかが退職した場合でも支払いは残る」といったデメリットも存在するため、ペアローンはやめた方が良いと言われることも少なくありません。
そこで今回は、ペアローンを利用しようか迷っている方へ、ペアローンの概要、メリットやデメリット、収入合算との違いについて、一番多い夫婦の形を例に挙げて解説していきます。ペアローンを組んだ後に離婚してしまった場合にどのようになるのか、育休中での住宅ローン申請は可能なのかなどについても触れますので、ペアローンを利用するかどうかの判断材料としてぜひ参考にしてくださいね。
目次 |
ペアローンとは?

まずは、ペアローンとはどのような借入方法なのかご紹介しましょう。一般的な住宅ローンとの違いは、次の通りです。
| 単独ローン
(夫1名による借入) |
ペアローン
(夫婦など2名での借入) |
|
| 契約者 | 夫のみ | 夫・妻 |
| 契約の数 | 1本 | 2本 |
| 連帯保証人 | – | それぞれがお互いの連帯保証人になる |
| 団信への加入 | 夫のみ | 夫・妻 |
| 住宅ローン控除の利用 | ||
| 所有権 |
これを踏まえた上で、ペアローンならではの特徴2点はこちらです。
| ペアローンの2つの特徴 |
| 夫婦それぞれで住宅ローンを契約する
住宅の所有権が共有名義になる |
それぞれ分かりやすく説明していきましょう。
夫婦それぞれで住宅ローンを契約する
一般的な住宅ローンは世帯の代表者1名が1本の契約でローンを組みます。一方のペアローンでは、夫婦や親子など2名がそれぞれ契約者となって住宅ローンを組む形になり、お互いが相手の契約の連帯保証人となります。つまり、住宅ローンの対象となる物件は1つですが、契約は2本です。
契約数は2本になりますので、住宅ローン控除や団体信用生命保険への加入についても、2人共それぞれ利用できます。住宅ローン控除については、後ほど詳しく解説します。
住宅の所有権が共有名義になる
夫単独ローンの場合、住宅の所有権はもちろん夫のみとなりますが、夫婦でペアローンを組んだ場合には、住宅の所有権は共有名義となります。これは親子でのペアローンのケースでも同様です。
ちなみに共有する所有権の持分は、それぞれが負担した割合に応じて決められることが多いです。たとえば、5,000万円の注文住宅を建てるために夫婦でペアローンを組んだ場合の持分は、以下のようになります。
【ペアローンによる住宅の所有権の割合(例)】
| 負担割合 | 共有持分の割合 | |
| 夫 | 自己資金1,000万円(頭金)
住宅ローンにて2,000万円借入 →合計3,000万円の負担 |
3/5 |
| 妻 | 自己資金500万円 住宅ローンにて1,500万円借入→合計2,000万円の負担 |
2/5 |
ペアローンのメリット

住宅の購入を目的に、夫婦でペアローンを組む場合、次のようなメリットがあります。
| ペアローンを利用する際の主なメリット |
| 借入額を増やす事ができる
住宅ローン控除を夫婦それぞれで利用できる 夫婦で返済条件を変えることができる |
それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。
借入額を増やすことができる
ペアローンの一番のメリットは「借入額を増やせること」です。夫一人の収入では手が届かない物件でも、妻とのペアローンにした場合には購入の対象に入れられる可能性が高くなります。
住宅ローンの借入可能額は、年収・属性の高さ・勤務歴・資産状況などによって決定されます。融資元の金融機関側としても、返済能力が高いと判断できるローン申請者には、できるだけ多く貸し出したいと考えます。たとえば、正社員で勤務歴が長く安定した収入がある場合には「属性が高い」と判断され、審査に通りやすいだけでなく、借入可能額も大きくなります。
ペアローンでは返済能力のある2名がそれぞれローンを組むことになりますので、2人の借入可能額を合計することで、単独ローンよりも借入可能額が増えることになるのです。
住宅ローン控除を夫婦それぞれで利用できる
ペアローンを組んだ場合には、夫婦2人がそれぞれ住宅ローン控除を利用できますので、節税になります。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを建てたり増築したりした場合に、一定の条件を満たす人を対象に、ローン金利の負担を軽減してくれるという制度です。具体的には原則10年間(最大13年間)、毎年末における住宅ローン残高の0.7%分が所得税額や住民税から控除されます。
新築住宅を建てた場合に適用となる住宅ローン控除の詳細は次の通りです(令和6年2月時点)
【住宅ローン控除の適用条件/新築住宅を建てた場合】
| 区分 | 借入限度額 | 1年間の控除額 | 控除期間 | 最大控除額 |
| 令和6年・7年入居 | ||||
| 長期優良住宅
低炭素建築物 |
4,500万円 | 31.5万円 | 13年 | 409.5万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 24.5万円 | 13年 | 381.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 21万円 | 13年 | 273万円 |
| その他一般新築住宅 | 2,000万円 | 14万円 | 10年 | 140万円 |
| 控除率 | 0.7% | |||
| 所得要件 | 合計で2,000万円以下 | |||
| 床面積要件 | 50m2以上 | |||
※一般の新築住宅のうち、令和5年12月末までに建築確認を受けたもの、令和6年6月末までに建築されたものに限る
夫婦で返済条件を変えることができる
ペアローンを組んだ場合、夫婦それぞれで異なるローン金利を選ぶことができます。
住宅ローンの金利には、基本となる「固定金利」と「変動金利」という2種類の他、最初の一定期間は固定金利+その後変動金利に切り替わるという「固定金利選択型」もあり、それぞれメリットやデメリットが異なります。たとえば夫は変動金利、妻は固定金利など、異なるローン金利を選ぶことで、金利上昇時に負担増となるリスクを抑えられる可能性を上げることができます。
ペアローンのデメリット

メリットが多いペアローンですが、次のようなデメリットもあります。後悔しないためにも、良い面だけでなくデメリットもしっかり把握しておくことが大切です。
| ペアローンを利用する際の主なデメリット |
| 諸費用が2倍になる
どちらかが退職した場合も支払いは残る |
こちらも詳しく見ていきましょう。
諸費用が2倍になる
ペアローンでは1つの物件に対してローン契約が2本になりますので、契約1本毎に発生する諸費用は2倍かかると考えてください。
住宅ローンを組む際にかかる諸費用にはいくつか種類がありますが、このうちペアローンで負担額が増えるのは、融資事務手数料・印紙税・司法書士への報酬(抵当権設定登記を依頼)・保証会社事務手数料などです。
【住宅ローン諸費用のうちペアローンで負担が増えるもの】
| 単独ローンの場合 | ペアローンの場合 | ||
| 融資事務手数料 | ネット銀行 | 借入金額×約2.2% | それぞれの(借入金額×約2.2%)の合計 |
| 都市銀行 | 約3万3,000円 | 約3万3,000円×2 | |
| 印紙代 | 2万円 | 2万円×2 | |
| 司法書士への報酬 | 約3万~5万円 | 約5万円~ | |
| 保証会社事務手数料 | 3万3,000円~ | 3万3,000円×2~(※) | |
※審査の結果、保証会社を利用する場合
たとえば印紙税ですが、ローン契約金額が1,000万円超5,000万円以下の場合は2万円かかりますので、ペアローンでは契約本数が2本で合計4万円の印紙税がかかることになります。ただし、電子契約で手続きを行う場合には0円です。
抵当権設定登記については司法書士へ依頼するケースが多く、ローン契約1本につき約3万~5万円の報酬を支払うことになります。依頼する司法書士によりますが、ペアローンでは単純に2倍とはならないものの、上乗せ費用は必要になることが多いです。
保証会社事務手数料については、ペアローンではお互いがお互いの連帯保証人となりますので、基本的にかかりませんが、審査の結果次第では保証会社の利用が必要となるケースもあります。この場合、保証会社に対する連帯保証人となります。ただし、融資元の金融機関で保証会社事務手数料を0円設定としている場合にはかかりません。
諸費用は金融機関により計算方法が異なりますので、利用しようと考えている住宅ローンの設定に基づいて試算してみることが大切です。
どちらかが退職した場合も支払いは残る
夫婦でペアローンを組み、どちらかが退職した場合でも、それぞれのローンは独立したものですので契約は維持されます。ローン返済は残るものの、退職で収入がなくなると所得税も発生しないことになりますので、住宅ローン控除も受けられなくなってしまいます。
ペアローンから単独ローンへの借り換えを検討するケースもありますが、所有権の変更や贈与となる可能性もあることから難易度が高いため、現実的には難しい傾向にあります。
人生でどんなことが起こるのか予想するのは難しいものですが、どちらかが働けなくなってしまう可能性もゼロではありません。ペアローンを組む際は、片方が退職せざるを得なくなった場合の返済計画についても、二人で話し合っておくことをおすすめします。
収入合算との違い

ペアローンと似ている住宅ローンの種類として「収入合算」というものもあります。どちらも借入可能額が上がるというメリットは同じです。こちらでは、収入合算とはどのような住宅ローンなのか、ペアローンとどのように違うのかについて解説していきます。
住宅ローンにおける収入合算とは、一定の収入がある夫婦や親子など2名の収入を合算して、1つのローン契約とする方法です。主となる契約者(主債務者)がいて、もう片方は契約者の連帯保証人または連帯債務者となります。連帯債務者とは、契約者と同等の返済義務がある人のことです。
収入合算には「連帯保証型」と「連帯債務型」という2つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。ペアローンも含め、違いを表にしてみました。
| ペアローン
(夫婦2名での借入の場合) |
収入合算
(主債務者:夫、収入合算者 妻の場合 |
||
| 連帯保証型 | 連帯債務型 | ||
| 契約者 | 夫・妻 | 夫 | |
| 契約の数 | 2本 | 1本 | |
| 連帯保証人 | それぞれがお互いの連帯保証人になる | 妻 | 連帯債務者:妻 |
| 団信への加入 | 夫・妻 | 夫 | 夫のみor夫婦連生団信であれば妻も加入可能 |
| 住宅ローン控除の利用 | 夫・妻 | ||
| 所有権 | |||
ペアローンでは夫婦それぞれが住宅ローンを契約しますので、合計で2本の契約となります。対する収入合算では、契約者(夫)の収入にもう1人(妻)の収入を合算して1本の住宅ローン契約として扱われます。そのため、まず挙げられる違いとしては「収入合算ではペアローンよりも住宅ローンの諸費用を抑えることが可能」だという点です。
また、収入合算の「連帯保証型」と「連帯債務型」の2つの種類の間でも、異なる点があります。夫婦で収入合算を利用し、「夫が主債務者(ローン契約者)、妻が収入を合算する側」を例に挙げて、それぞれ詳しく見ていきましょう。
連帯保証型
収入合算の連帯保証型では、妻が夫(主債務者)の「連帯保証人」となるのが特徴の1つです。連帯保証人は主債務者が返済できなくなった時に返済義務を負いますが、原則として主債務者が返済をしっかりと行う必要があります。
また、団体信用生命保険への加入や住宅ローン控除の利用ができるのは夫のみです。収入合算であっても連帯保証型では、物件の所有権についても夫のみ となります。あくまでも、主債務者である夫がメインとなっていると考えてください。
連帯債務型
一方の収入合算の連帯債務型では、妻が夫(主債務者)の「連帯債務者」となります。連帯債務者はローン返済の開始直後から主債務者と同等の返済義務を負います。そのため、住宅ローン控除の利用や物件の所有権保有についても、夫・妻の双方が可能です。
団体信用生命保険への加入については、原則としては夫のみとなります。ただし、融資元の金融機関で「夫婦連生団信」を取り扱っている場合には、連帯債務者である妻も団信に加入可能です。
収入合算の連帯債務型を提供している金融機関は少ないですので、利用したい場合には住宅ローンを利用できる金融機関が限られることにご注意ください。
ペアローンでよくある質問

こちらでは、ペアローンを検討中の多くの方々からよく聞かれる質問2つについて、解説していきます。
もし離婚してしまったら?
ペアローンを組んだ後に離婚となってしまった場合、共有財産となっている家も財産分与の対象となります。離婚による財産分与では「半分ずつ」が原則です。そこで、「家を売却する」または「どちらかが家に住み続ける」のどちらかの方法を行うことになります。
それぞれのケースについて詳しく解説していきましょう。
- 家を売却する
双方合意の上でペアローン付き物件を他者へ売却し、売却益を夫婦で折半、それぞれがそのお金をローン返済に充て清算するという方法です。家の売却額がローン残債よりも高い場合には、財産分与をスムーズに行えるでしょう。
ただし、家の売却額がローン残債よりも低かった場合には、自身のローン返済に自己資金も投入しなければなりません。この場合、売却は難しいかもしれません。
- どちらかが家に住み続ける
この場合はさらに「住み続ける方が家の所有権を譲り受ける」もしくは「それぞれが自身の分のローン返済を続けていく」のどちらかを選択することになります。
前者の場合は、譲渡された側が、もう片方へ物件の査定額の半分を支払います。後者の場合、離婚後もお互いが連帯保証人であることに変わりありませんので、万が一どちらかの返済が滞れば、自分のローン返済に加えて相手の分も返済する必要が出てきます。
離婚した場合でも、ペアローンの契約自体は生きていますので、返済状況によって慎重に選ぶ必要があるでしょう。
育休中でも住宅ローンは組めるのか
結論から言えば「将来的に、安定した収入が継続する見込みのある方」であれば、育休中でも住宅ローンの申請は可能なケースが多いです。たとえばSBI新生銀行の場合、次のような条件を満たせばローン申請はできます。
| 復職後の年収(見込)300万円以上(収入合算者では200万円~)であること
審査時に復職後の年収を証明するものを提出すること |
基本的に復職前提となっていますが、金融機関によって条件は異なりますので、対応してくれるところを探す必要があります。審査の際には、見込年収証明書・育休証明書などの書類が追加で必要になるケースもありますので、事前にご確認ください。
まとめ
借入額を増やせるなど多くのメリットがあるペアローンですが、ローンを組む際の諸経費が約2倍になったり、離婚の際には手間がかかったりといったデメリットも存在します。将来的に2人とも安定した収入が見込める場合にはペアローンがおすすめですが、しっかりとした資金計画を立てておくことが大切でしょう。
おうちモールでは、ファイナンシャルプランナーが各家庭に合わせた返済シミュレーションを作成し、アドバイスをいたします。すべて無料でご相談可能ですので、お気軽にご相談ください!
おうちモールは、FPや宅建などの国家資格を持つプロのアドバイザーが
あなたにピッタリの住宅会社をご紹介する注文住宅の相談窓口です。
\ 資金計画相談もメーカー比較・紹介もすべて完全無料です /
おうちモール公式サイトへ
注文住宅の営業担当者は変更できる?担当の決まり方や優秀な担当者に出会う方法を解説!
前の記事へ
【2024年度版】注文住宅で利用できる補助金や減税制度完全ガイド

次の記事へ